【2025年最新】歯科医院が医療広告ガイドラインで注意すべき表現とNG例を分かりやすく解説
はじめに:知らないでは済まされない医療広告ガイドライン
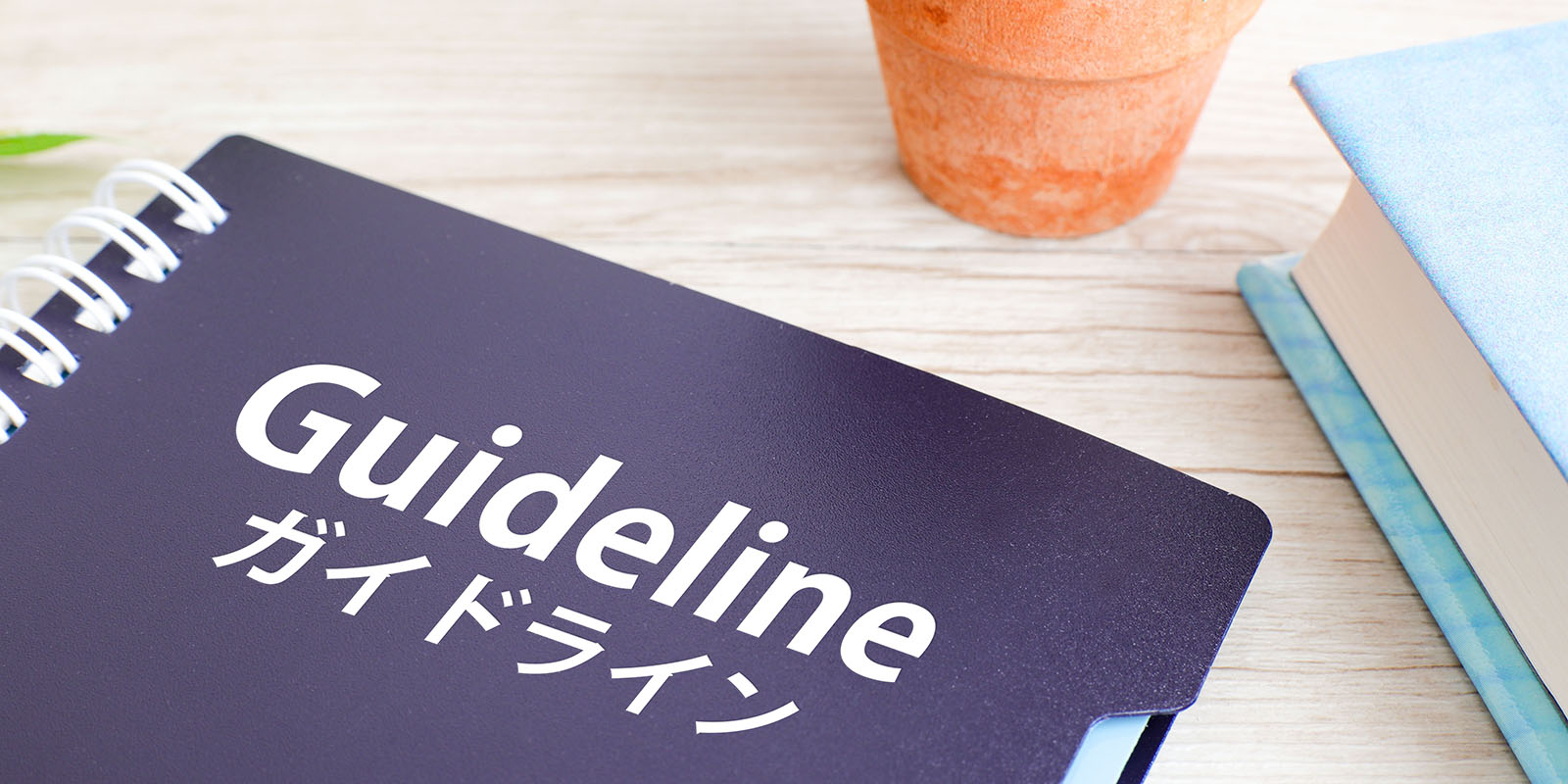
「当院は地域No.1の実績」「絶対に痛くない治療」「口コミ評価★5つ」――こうした表現、あなたの歯科医院のホームページやチラシで使っていませんか?実は、これらはすべて医療広告ガイドラインに違反する可能性が高い表現です。
2018年に医療広告ガイドラインが改正され、ウェブサイトも規制対象となりました。違反した場合、行政指導や最悪の場合は罰則の対象になることもあります。
しかし、法律用語が並ぶガイドラインは理解しづらく、「何がOKで何がNGなのか分からない」という声を多く聞きます。本記事では、歯科医院が特に注意すべき医療広告ガイドラインのポイントを、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
そもそも医療広告ガイドラインとは?
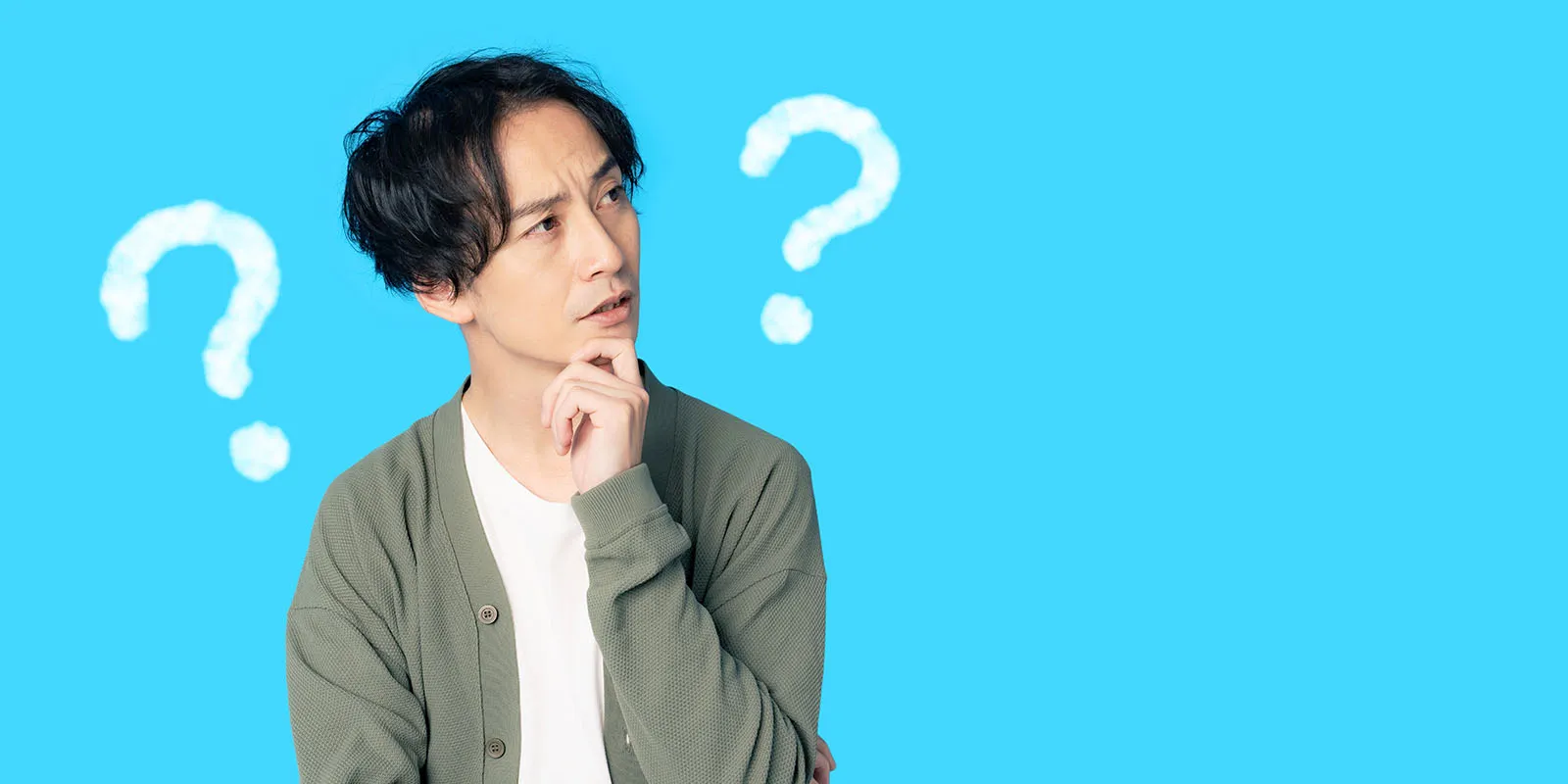
医療広告ガイドラインは、厚生労働省が定める「医療法」に基づいた規制です。その目的は、患者さんを誤解や混乱から守り、適切な医療機関選択をサポートすることにあります。
2018年改正の重要ポイント
従来は看板や新聞広告などが規制対象でしたが、2018年の改正により、ホームページ、ブログ、SNSなど、インターネット上の情報もすべて広告とみなされるようになりました。これは「ネット広告だから大丈夫」という時代が終わったことを意味します。
特に歯科医院の場合、審美歯科やインプラント、ホワイトニングなど自費診療の情報発信が多く、規制に抵触しやすい傾向があります。自院のウェブサイトだけでなく、歯科ポータルサイトへの掲載内容、Googleビジネスプロフィールの説明文なども規制対象です。
規制対象となる「広告」の定義
医療広告として規制されるのは、次の2つの要件を満たすものです。第一に、患者さんの受診を誘引する意図が明確であること。第二に、医療機関の名称や診療科目など、特定が可能な情報が含まれていること。
つまり、あなたの歯科医院名や所在地が記載され、来院を促す内容であれば、それは「広告」として規制対象になるということです。ブログ記事であっても、SNS投稿であっても、この定義に当てはまれば規制を受けます。
絶対に避けるべき禁止表現7つのパターン

医療広告ガイドラインで明確に禁止されている表現を、歯科医院でよく見られる具体例とともに解説します。
1. 比較優良広告
他の医療機関と比較して自院が優れていると示す表現は、明確に禁止されています。
NG例
- 〇〇市で一番の実績」
- 「地域No.1の患者満足度」
- 「他院では難しい治療も可能」
- 「業界最先端の設備」
これらは客観的な根拠があったとしても使用できません。「一番」「最高」「最先端」といった最上級表現は、基本的にすべてNGと考えてください。
OK例
- 「年間〇〇件の治療実績」(具体的な数字のみ)
- 「〇〇の設備を導入しています」(事実のみの記載)
2. 誇大広告
事実を誇張したり、過度に強調したりする表現も禁止されています。
NG例
- 「絶対に痛くない治療」
- 「必ず白くなるホワイトニング」
- 「100%成功するインプラント」
- 「どんな症状でも治せます」
医療には必ず個人差があり、「絶対」「必ず」「100%」といった断定表現は使用できません。
OK例
- 「痛みに配慮した治療を心がけています」
- 「麻酔方法を工夫することで、痛みの軽減に努めています」
3. 体験談・口コミの掲載
患者さんの体験談や口コミの掲載は、原則として禁止されています。これは多くの歯科医院が誤解しているポイントです。
NG例
- ホームページに患者さんの声を掲載
- 「〇〇さん(40代女性)のコメント」として感想を紹介
- Googleの口コミをホームページに転載
- Instagramのコメントをスクリーンショットで掲載
第三者が投稿した口コミサイトの内容そのものは問題ありませんが、それを自院のホームページやSNSで引用・掲載することは禁止されています。
例外的にOKな例
- 患者満足度調査の結果を、調査方法や回答者数などの詳細情報とともに掲載する場合(ただし、任意回答であることなど一定の条件を満たす必要あり)
4. Before/After写真の不適切な掲載
審美歯科やホワイトニングの症例写真は、一定の条件を満たさなければ掲載できません。
NG例
- 治療前後の写真のみを掲載(説明なし)
- 「誰でもこうなります」という印象を与える掲載方法
- 明らかに効果を強調した加工写真
- リスクや副作用の説明がない症例写真
第三者が投稿した口コミサイトの内容そのものは問題ありませんが、それを自院のホームページやSNSで引用・掲載することは禁止されています。
OKな例
治療前後の写真を掲載する場合は、以下の情報をすべて併記する必要があります。
- 治療内容の詳細説明
- 治療期間と費用
- 主なリスクや副作用
- 「効果には個人差があります」という旨の注意書き
- 通常必要とされる治療内容との比較
5. 虚偽広告
事実と異なる内容の掲載は当然ながら禁止です。
NG例
- 実際には常勤していない歯科医師を「在籍」と表示
- 取得していない専門医資格を記載
- 導入していない設備を「完備」と表示
- 対応していない診療科目を掲載
これは意図的でなくても、更新漏れで違反になるケースがあります。特にスタッフの異動や設備の入れ替え後は、ホームページの情報も必ず更新しましょう。
6. 客観的事実を証明できない内容
根拠を示せない表現も禁止されています。
NG例
- 「満足度95%」(調査データの提示なし)
- 「多くの患者様に選ばれています」(具体的数値なし)
- 「高い技術力」(客観的評価基準なし)
- 「安全性が高い治療」(根拠の提示なし)
OKな例
- 「当院で実施した患者満足度調査(〇年〇月実施、回答数〇名)の結果、95%の方から『満足』という評価をいただきました」
- 「〇〇学会認定医が在籍しています」(認定証の提示可能な場合)
7. 品位を損なう内容や過度な期待を抱かせる表現
社会的妥当性を欠く表現や、誤解を招く表現も禁止されています。
NG例
- 「芸能人も通う歯科医院」
- 「今だけ限定、格安インプラント」
- 「キャンペーン価格でホワイトニング」
- 費用の一部のみを強調した表示(総額の明示がない)
医療は営利目的のサービスではないため、過度に商業的な表現は避けるべきです。
グレーゾーンの表現、どこまでOK?

実務上、判断に迷う表現について解説します。
「〇〇認定医」「専門医」の表記
学会が認定する資格は、その学会が法人格を持ち、一定の基準を満たしている場合のみ掲載可能です。日本歯周病学会、日本口腔外科学会など、広告可能な学会は厚生労働省のウェブサイトで確認できます。自称の「〇〇専門」「〇〇エキスパート」といった表現は使用できません。
「無痛治療」の表現
「無痛」という言葉自体が誇大広告とみなされる可能性があります。「痛みの少ない治療」「痛みに配慮した治療」など、配慮や工夫を示す表現に留めるのが安全です。
「〇〇相談会」「無料検診」の案内
イベント告知そのものは問題ありませんが、「無料」を過度に強調したり、イベント参加を誘引するために誇大な表現を使ったりすることは避けてください。実施内容と費用を明確に記載することが重要です。
メディア掲載実績
「〇〇雑誌に掲載されました」という事実の記載は可能ですが、それを自院の優良性の根拠として強調することは避けるべきです。あくまで事実の記載に留め、「だから当院は優れている」という印象を与えないよう注意しましょう。
限定解除という特例措置

医療広告ガイドラインには「限定解除」という特例があります。これは、一定の条件を満たせば、通常は広告できない情報も掲載可能になる仕組みです。
限定解除の要件
以下の4つすべてを満たす必要があります。
- 医療に関する適切な選択を支援する目的であること
- 患者さん自らが求めて情報を取得する場合であること(検索サイト等で自発的にアクセスした場合など)
- 問い合わせ先を明記していること
- 自由診療の場合、費用やリスク・副作用について詳細に記載していること
限定解除で可能になること
たとえば、詳細な治療内容の説明、専門的な治療法の紹介、未承認医薬品や医療機器の使用に関する情報などが掲載可能になります。
ただし、限定解除を適用しても、虚偽広告や誇大広告は認められません。あくまで「客観的で正確な情報提供」という範囲内での解除です。
違反した場合のペナルティ
医療広告ガイドラインに違反した場合、以下のような措置が取られる可能性があります。
行政指導
まず、都道府県や保健所から是正指導が入ります。期限を設けて改善を求められ、従わない場合は次のステップに進みます。
命令と罰則
改善命令に従わない場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、悪質なケースでは医院名が公表されることもあり、信用問題に発展します。
民事上のリスク
ガイドライン違反の広告により患者さんが不利益を被った場合、損害賠償請求される可能性もゼロではありません。
今日から始める5つのチェックポイント

自院の広告内容が適切か、以下のポイントでチェックしましょう。
1. ホームページ全体の見直し
トップページから各診療科目のページまで、すべてのページで禁止表現が使われていないか確認します。特に、開設当初から更新していないページは要注意です。
2. Googleビジネスプロフィールの確認
ビジネスの説明欄、投稿内容、提供サービスの記載などをチェックしてください。ここも医療広告ガイドラインの対象です。
3. SNS投稿の見直し
過去の投稿で不適切な表現がないか確認し、問題があれば削除または修正します。今後の投稿ルールも明確にしておきましょう。
4. 料金表示の適正化
自費診療の料金は、総額を明示し、治療期間やリスクとセットで記載されているか確認してください。一部の金額のみを強調した表示は避けます。
5. 定期的なチェック体制の構築
スタッフが新しくブログを投稿する際、広告ガイドラインに準拠しているかチェックする体制を作りましょう。チェックリストを作成しておくと便利です。
よくある質問
Q1: 個人のSNSアカウントでの投稿も規制対象ですか?
院長個人のアカウントであっても、医院名や診療内容を含み、受診を誘引する内容であれば規制対象になります。完全にプライベートな投稿でない限り、注意が必要です。
Q2: 歯科ポータルサイトに掲載する情報も規制されますか?
はい、規制対象です。ポータルサイトの運営会社に掲載内容の確認を依頼し、ガイドラインに準拠しているか確認してください。
Q3: 海外で承認されている治療法や機器の情報は掲載できますか?
限定解除の要件を満たせば掲載可能ですが、国内未承認であることを明記し、リスクや費用を詳細に記載する必要があります。
Q4: 患者さんから「口コミを書いてほしい」と頼まれた場合は?
患者さん自身がGoogleやエキテンなどの第三者サイトに投稿することは自由です。ただし、医院側から依頼したり、謝礼を渡したりすることは避けるべきです。
Q5: スタッフブログでの表現も気をつける必要がありますか?
医院の公式サイト内のブログであれば、当然規制対象です。スタッフが書く場合も、院長が内容をチェックする体制を整えましょう。
まとめ:患者さんとの信頼関係を守るためのガイドライン
医療広告ガイドラインは、決して歯科医院を縛るためのものではありません。患者さんを誤解から守り、適切な情報提供を行うための指針です。
規制を「面倒なルール」と捉えるのではなく、「患者さんとの信頼関係を構築するための基準」として前向きに理解することが大切です。誇大な表現に頼らなくても、誠実で正確な情報発信によって、患者さんの信頼は必ず獲得できます。
今日からできることは、まず自院のホームページやSNSを見直すことです。不安な表現があれば専門家に相談するか、より安全な表現に修正しましょう。適切な情報発信こそが、長期的な集患と信頼構築につながります。
コンプライアンスを守りながら効果的な情報発信を行うことは、決して矛盾しません。むしろ、ガイドラインを理解し遵守することで、患者さんに選ばれ続ける歯科医院を作ることができるのです。

